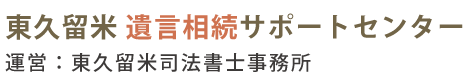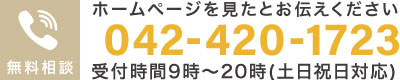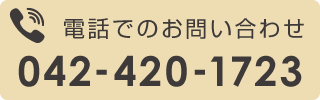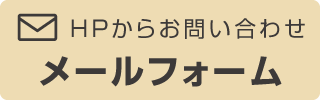Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 274 海外で亡くなった場合の死亡届
Q274
海外で亡くなった場合、どこに死亡届を提出すればよいのですか?
A274
海外で亡くなった場合、原則として現地(海外)の意思に死亡診断書を書いてもらい、大使館や領事館に死亡届を提出することになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 273 火葬許可申請書
Q273
相続が発生したのですが、火葬許可申請書はどこに提出すればよいのでしょうか?
A273
火葬許可申請書は、通常、死亡届と同時に市区町村役場へ提出することになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 272 相続財産と未登記不動産
Q271
未登記の不動産であっても相続財産に含まれますか?
A271
未登記不動産であっても、実質的に被相続人に帰属する財産は相続財産に含まれます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 270 遺産分割の方法
Q270
遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?
A270
遺産分割の方法には以下のようなものがあります。
①現物分割
→遺産を現物のまま分割する方法です。
②換価分割
→遺産の一部または全部を金銭に換え、その換価代金を分割する方法です。
③代償分割
→共同相続人中の一人または数人が遺産の現物を取得する代わりに、取得した者が他の相続人に対して、自己の財産を与える方法です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 262 相続人が複数いる時の相続税の申告
Q262
相続人が複数いる場合、その内の一人が相続税申告を済ませれば問題ないでしょうか?
A262
いいえ。
相続税額を計算した結果、納めるべき税額が発生する人及び一定の特例措置の適用を受ける人は、
相続税の申告書を提出する必要があります。
一人の被相続人につき、申告を要する人が複数人いる場合は、
その全員が申告書を提出しなければなりません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 261 準確定申告が必要な場合
Q261
準確定申告はどんな場合に必要なのでしょうか?
A261
被相続人が生前に個人事業を営んでいるなど、確定申告を要していた場合が多いです。
一方給与取得者については、給与支給者が年末調整により税額の算出等を行うので、確定申告は不要である場合が多いです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 260 準確定申告
Q260
準確定申告とはなんですか?
A260
準確定申告とは、被相続人の所得にかかる所得税についての手続きです。
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に所得が生じた場合において、
相続開始があったことを知った日の翌月から4ヶ月以内に、相続人が行う確定申告のことをいいます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 258 相続税の申告・納付の遅滞
Q258
相続税の申告期限までに申告・納付をしないとどうなるのですか?
A258
相続税が申告期限までに申告・納付されない場合は、
原則として
(1)無申告加算税(申告遅滞に対してのペナルティ)
(2)延滞税(納付遅滞に対してのペナルティ)
が課せられます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 252 遺言による推定相続人の廃除
Q252
遺言で推定相続人を廃除することはできるのですか。
A252
はい、可能です。
民法第893条において、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない」と定められています。
この場合、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 251 推定相続人の廃除
Q251
推定相続人を廃除することはできるのですか。
A251
はい、可能です。
「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。