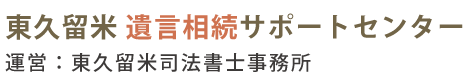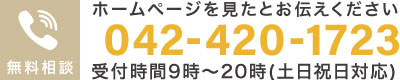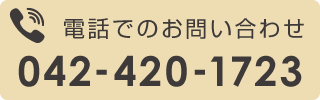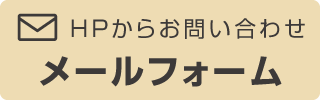Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 309 代襲相続と特別受益
Q309
代襲相続があった場合の特別受益について教えてください。
A309
代襲相続があった場合、特別受益については、代襲原因が発生した後の代襲者の受益分に関しては、特別受益として考慮されると考えられています。
(参考)福岡高判平29・5・18判時2346・81

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 308 遺産分割のやり直しと課税問題
Q308
遺産分割をやり直す場合、注意することはありますか?
A308
遺産分割をやり直すと、贈与税や譲渡所得税が発生してしまうリスクがあります。
必ず相続に強い税理士等の専門家までご相談ください。
(参考)東京高判平12・1・26税資246・205

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 307 遺産分割が不要な場合
Q307
遺産分割が不要な場合はありますか?
A307
以下のいずれかの場合、遺産分割をする必要がありません。
(1)遺言によって、遺産分割の対象となる相続財産全体の処分方法等が指定されている場合。
(2)相続人が一人しかいない場合。
(3)遺産分割の対象となる相続財産が存在しない場合。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 304 贈与と不動産取得税
Q304
贈与をした際に、不動産取得税はかかるのですか?
A304
贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税がかかります。
一方、相続によって不動産を取得した場合には、不動産取得税がかからず、相続税がかかるのみです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 301 贈与税の非課税財産
Q301
贈与税の課税対象とならない財産はどんなものがありますか・
A301
原則として、贈与を受けた財産は贈与税の課税対象となりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて
贈与税の課税対象とすることが適当でないと認められているものは、贈与税の非課税財産とされています。
(1)会社や法人から贈与された財産 ※所得税の課税対象になる
(2)扶養義務者からの生活費または教育費
(3)公益を目的とする事業によって取得された財産で同事業に使用されることが確実なもの
(4)特定公益信託等から交付される奨学金
(5)心身障害者共済制度に基づいて受けた給付金
(6)公職選挙法の適用を受ける選挙候補者が選挙運動で取得した金品
(7)特定障害者不要信託契約に基づく信託受益権
(8)香典、花輪代、見舞いなどの社会通念上相当と認められる金品
(9)相続開始の年に被相続人から受けた贈与 ※相続税の課税対象になる
(10)直系尊属から受けた住宅取得等資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの
(11)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの
(12)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 300 贈与税の課税財産
Q300
贈与税の課税対象となる財産はどれですか?
A300
贈与税の課税対象は「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」です。
【本来の贈与財産】
当事者間の契約によって取得した一切の財産
例.土地、家屋、事業用財産、貴金属、有価証券、預貯金など
【みなし贈与財産】
贈与契約がなくても実質的に贈与があった者と同様の経済的な効果があるもの
例.生命保険金、定期金、信託受益権、定額譲渡など

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 299 贈与契約書の作成
Q299
贈与契約書の作成を司法書士にお願いすることはできますか?
A299
贈与の対象に不動産が含まれている場合、司法書士は、贈与による登記の添付書類として贈与契約書を作成することができます。
しかし、贈与の対象に不動産が含まれていない場合には、司法書士が贈与契約書を作成することはできません。
この場合には、提携の弁護士をご紹介いたします。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 295 親権者と職業の許可
Q295
子は好き勝手に職業を営むことができますか?
A295
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができません(民法第823条)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 294 親権者
Q294
親権者は誰になるのですか?
A294
成年に達しない子は、父母の親権に服します(民法第818条)。
また、子が養子である場合は、養親の親権に服します(同条第2項)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 290 遺言と二次相続
Q290
遺言で以下のような内容を決めることはできますか?
(1)私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる。
(2)妻に相続させた財産は、妻の死後は長男のAに相続させる。
A290
(1)は問題ありません。
しかし、(2)については、既に妻の財産となっている以上、その財産の帰属を決めることができるのは妻のみとなります。
そのため、現時点で二次相続先まで遺言で指定することはできないのです。
このような事案をご希望の方は、家族信託を利用すると解決することができます。
ご興味のある方は、一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。