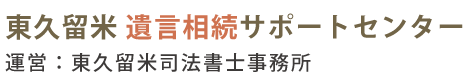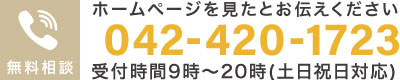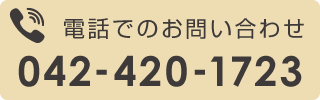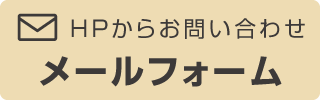Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 231 遺言書に使用するペン
Q231
遺言書は消せるボールペンで書いても良いのですか?
A231
厳密にいうと、「遺言はこの文房具を用いて書きなさい」という法律上の規定はありません。
そのため、消せるボールペンや鉛筆で遺言を書いたとしても、そのことをもって即無効になるということはありません。
しかし、鉛筆や消せるボールペン等は、改竄の恐れがあるので、後日紛争が生じる危険性が高いと言えます。
そのため、何か特別なご事情が無い限りは、ボールペンや万年筆のような消せないペンでの作成をオススメいたします。
東久留米司法書士事務所では、自筆証書遺言の作成支援も行っています。
どうぞお気軽にご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 230 遺贈と農地法の許可
Q230
相続人ではない叔父に農地を相続させるという遺言が見つかったのですが、この場合も農地法の許可は不要なのですか?
A230
A229でお答えしたとおり、相続人が農地を相続する場合の所有権移転登記申請においては、農地法の許可は不要です。
しかし、相続人ではない第三者に農地を取得させることは「遺贈」といい、この場合には農地法の許可が必要となります。
しかし、遺言書の内容から「包括遺贈」なのか「特定遺贈」なのかによっても結論が異なってきますので、まずは東久留米司法書士事務所までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 229 農地の相続と農地法の許可
Q229
農地の所有権を移転する場合には農地法の許可が必要だと聞いたのですが、本当ですか?
今回父の農地を私が相続することになったのですが、農地法の許可が必要になるのでしょうか?
A229
農地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び主益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、原則として農業委員会の許可を得なければなりません(農地法第3条1項柱書本文)。
しかし、相続による農地の承継は法律上当然に生じるものなので、上記農地法の許可は不要とされています。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 228 相続税の非課税財産
Q228
相続税の非課税財産にはどのようなものがありますか?
A228
以下の財産の価額は、相続税の課税価格に算入されません(相続税法第12条)。
(1)墓地、墓石、仏壇、祭具などの祭祀用財産
(2)生命保険金のうち500万円×法定相続人数
(3)死亡退職金のうち500万円×法定相続人数

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 227 相続と訴訟の承継
Q227
訴訟の継続中に父が亡くなってしまいました。
この訴訟はどのようにすればよいのでしょうか?
A227
訴訟が係属している裁判所に対して訴訟手続受継の申立てをし、相続人が訴訟を引き継ぐこととなります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 226 商標権と相続
Q226
先日、父が亡くなりました。
父は個人事業主として商店を切り盛りしており、店の屋号は商標登録されています。
個人事業としての商標権者亡くなった父の個人名義となっているのですが、相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか?
A226
商標権の移転は、相続その他の一般承継によるものを除いて、登録をしなければその効力を生じません(商標35条,特許98条)。
また、相続その他の一般承継の場合には、登録なしに第三者にその効力を対抗することができるものの、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならないとされています。
そのため、ご相談の事例では、相続による商標権移転登録申請書を、戸籍等の添付書面と併せて特許庁長官に提出する必要があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 225 相続放棄者の負う管理義務
Q225
相続放棄をした人が負う管理義務とは、どのようなものなのですか?
A225
相続放棄をした人が負う管理義務とは、自己の財産に対する注意義務と同一であるとされています。
いわゆる善良な管理者の注意義務(善管注意義務)よりも責任の軽減されたものです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 224 相続人全員が相続放棄した場合の管理義務
Q224
相続放棄をした人の管理義務は、いつなくなるのですか?
A224
相続放棄をした人の管理義務は、次順位の相続人が相続財産を管理することができる時まで継続します。
最近東久留米司法書士事務所には、次のようなご相談が非常に多く寄せられています。
【事案】
父が亡くなり、相続人は配偶者と子。父の父母や祖父母はすでに亡くなっており、父には兄が2名いる。
【よくあるご相談と回答】
このような事案で、相続人全員で相続放棄をしたいという方が、最近非常に多くいらっしゃいます。
例えば、子について考えてみましょう。
まず、子は相続放棄をしたことによって父の負債(マイナス)を引き継ぐことは無くなります。
しかし、次順位の相続人(父母や兄弟姉妹)が相続放棄をしてしまうと、「次順位の相続人が相続財産を管理することができる時」が到来しなくなってしまうのです。
このような場合に管理義務を無くしたいと考えるのであれば、「相続財産管理人」を選任する必要があります。
相続放棄は簡単なように見えて、その実、非常に多くの事態を考慮しなければならない案件です。
絶対に相続放棄を失敗したくないという方は、必ず相続に強い司法書士までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 223 相続放棄後の管理義務
Q223
相続放棄をしても管理義務を負うと聞いたことがあるのですが、これは本当ですか?
A223
相続放棄をすると、プラスもマイナスも一切引き受ける必要がなくなります。
しかし、自分が相続放棄をしたことによって相続人となった次順位の相続人が新たに相続財産の管理を始めることができる時まで、相続放棄をした人は「管理義務」を負うこととなります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 222 遺留分減殺請求権の消滅時効
Q99
遺留分減殺請求権には時効があるのですか?
A99
遺留分減殺請求権は、
① 遺留分を侵害された者が「相続の開始されたこと及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年(短期時効)
または
② 相続開始の時から10年(除籍期間)
で消滅します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。