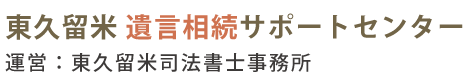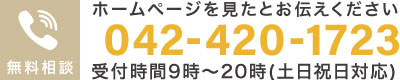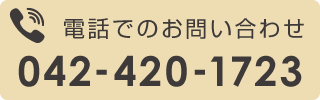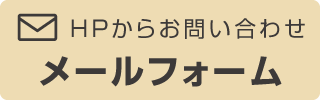Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 249 受遺者の死亡による遺贈の失効
Q249
遺贈者の死亡以前に受遺者が死亡しました。遺贈の効力はどうなるのですか?
A249
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 248 遺産の分割の効力
Q248
遺産分割の効力はいつから効力が発生しますか?
A248
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。
ただし、第三者の権利を害することはできません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 243 相続放棄と詐害行為取消
Q243
相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりますか?
A243
相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりません。
なお、遺産分割協議については、詐害行為取消権の対象となります(Q242参照)。
(参考)
最判昭49・9・20民集28巻6号1202頁

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 242 遺産分割協議と詐害行為
Q242
遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となりますか?
A242
遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となります。
(参考)
最判平11・6・11民集53巻5号898頁

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 241 行方不明者がいる場合の遺産分割協議
Q241
相続人が行方不明の場合、遺産分割協議はどのようにすればいいのですか?
A241
遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければ無効となります。
そのため、共同相続人間に行方不明者がいる場合、利害関係人の請求に基づいて家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、この不在者財産管理人と相続人との間で遺産分割協議が行われることになります(民法第25条1項)。
しかし、遺産分割という行為は財産処分的行為の要素を含むものであるため、遺産分割協議を開始するに際して家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第28条)。
連絡の取れない相続人がいる場合の相続手続きは、一筋縄ではいきません。
必ず、相続に強い司法書士や弁護士までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 240 遺産分割協議の当事者
Q240
遺産分割協議は誰を当事者としてするのですか?
A240
遺産分割協議の当事者は、以下の者です。
なお、これらの者のうち一部を除外してなされた遺産分割協議は、無効となります。
(1)共同相続人
(2)包括受遺者
(3)相続分を譲り受けた者
(4)遺言執行者

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 238 相互遺言
Q238
相互遺言とは何ですか?
A238
夫婦がお互いに「自分の財産は全て配偶者に相続させる。」と書いた遺言のことを、相互遺言といいます。
お互いに遺言を書くことによって、どちらが先にお亡くなりになったとしても、遺された配偶者の生活を保全することが可能となるのです。
子のいない夫婦が、お互いに自分の財産を相続させるとした遺言(相互遺言)を書くケースが良くありますが、
このような場合、遺言者夫婦の父母や祖父母が既にお亡くなりになっていれば、相続権は兄弟姉妹に移ります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がないので、結果として遺言者夫婦は誰からの請求も受けることなく、相互に財産を相続させあうことが可能となるのです。
この「相互遺言」は、東久留米司法書士事務所に最近非常に多く相談が寄せられています。
お考えの方はぜひ一度ご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 237 兄弟姉妹と遺留分
Q237
兄弟姉妹は遺留分額を請求することができないのですか?
A237
現行法上、兄弟姉妹に遺留分はありません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 236 遺留分を侵害する遺言
Q236
遺留分額を侵害する遺言を書いてもいいのですか?
A236
原則として、遺留分額を侵害する内容の遺言であっても有効です。
しかし、相続後に争いが顕在化しそうな場合には、最初から遺留分を考慮した遺言を書くことをオススメいたします。
また、兄弟姉妹には遺留分がないことにも注意が必要です。
遺言のことでお困りの方は、是非一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 232 遺言書の保管方法
Q232
作成した遺言書は、どのように保管しておけばいいのですか?
A232
遺言書の保管方法は、特に法律で決まっているわけではありません。
そのため、ご自宅のタンスの中や机の中、銀行の貸金庫等、どのような場所で保管していても構いません。
また、特定の相続人や第三者に預けていても構いません。
例えば、東久留米司法書士事務所でも、自筆証書遺言の作成と同時にその保管も承ることが多々あります。
紛失や改竄の恐れが無いのであれば、遺言者様の好きなようにして構わないのです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。