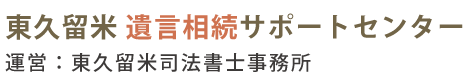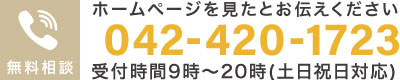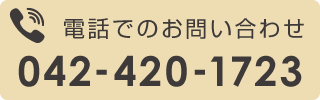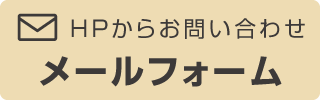Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 179 養子の相続分
Q58
養子の相続分は、雑誌の相続分と異なりますか?
A58
以前までは、養子の相続分は実子の相続分の2番の1とされていました。
しかし、近年の法改正によって、養子の相続分と実子の相続分は同じとなりました。
相続Q&A 178 胎児と相続
Q57
胎児は相続人となることができるのですか?
A57
胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます(民法第886条1項)。
相続Q&A 177 実子と養子の相続順位
Q56
実子と養子の間で相続の順位に差はありますか?
A56
実子と養子との間に相続の順位の差はありません。
相続Q&A 176 法定相続人と配偶者
Q55
配偶者は法定相続人になるのですか?
A55
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
しかし、ここでいう「配偶者」とは法律上の配偶者ですので、すでに離婚した者や内縁の配偶者は含みません。
相続Q&A 175 失踪宣告と相続開始時期
Q54
失踪宣告がされたときには、いつ相続が開始するのですか?
A54
相続の開始時期は、被相続人が死亡したときです。
しかし、普通失踪の場合には失踪期間が満了したときに、特別失踪の場合には危難が去った時に、被宣告者が死亡したものとみなされます。
相続Q&A 174 危急時遺言
Q53
危急時遺言とは何ですか?
A53
危急時遺言については、民法第976条に規定があります。
(死亡の危急に迫った者の遺言)
- 第976条
- 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
- 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
- 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
- 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
- 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
相続Q&A 173 養子の氏
Q52
養子の氏はどのようにして決まるのですか?
A52
養子は、養親と同じ氏を称することとなります。
しかし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りではありません。
相続Q&A 172 離縁と養子の氏
Q51
離縁をした場合、養子の氏はどうなるのですか?
A51
離縁をした場合、養子の氏は、縁組前の氏に戻ります。これを「復氏」といいます。
しかし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りではありません。
相続Q&A 171 相続人不存在と相続財産
Q50
相続人がいない場合、相続財産はどうなるのですか?
A50
相続人がいない場合や相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は法人となります。
相続Q&A 170 限定承認をしたときの権利義務
Q50
限定承認をした場合、被相続人に対して有した権利義務はどうなるのですか?
A50
相続人が限定承認をした場合、被相続人に対して有した権利義務については、消滅しなかったものとみなされます。
これは民法第925条に規定があります。
« Older Entries Newer Entries »