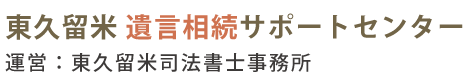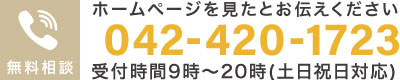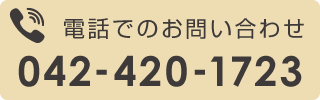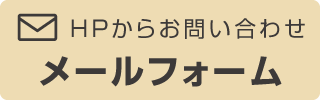Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 221 遺留分と事業承継
Q98
長男に事業承継をさせたいと考えているのですが、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、事業に影響が出てしまいかねません。
どうすれば良いのでしょうか?
A98
ご質問のように、共同相続人から遺留分の主張をされてしまうと、円滑な事業承継ができなくなる恐れがあります。
そこで、一定の要件を満たす相続人(事業を承継する者)が、遺留分権利者である共同相続人全員の合意と所定の手続きを経ることを条件として、自社株式等や自社株式等以外の財産を遺留分の対象から除外する特例が民法上設けられています。
詳しくは、相続に強い専門家までお問い合わせください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 220 自筆証書遺言の方式
Q97
自筆証書遺言に方式の要件はありますか?
A97
自筆証書は、全文・日付・氏名を自書し、押印しなければならないとされていました。
しかし、相続法の改正により、財産目録についてのみ自書しなくても良いこととなりました。
詳しくはお気軽にお尋ねくださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 210 検認の避け方
Q87
検認をしないで済むためにはどうすれば良いですか?
A87
一番よい方法は、公正証書遺言を作成することです。
公正証書遺言の場合は、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。
また、その原本が公証役場において保存されるので、紛失や書き換えの心配がありません。
その他、相続法の改正によって、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まっています。
この場合には、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。
詳しくは、東久留米司法書士事務所までお問い合わせください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 209 検認と過料
Q86
検認手続きを経ずに遺言執行してもいいのですか?
A86
検認を経ないで遺言執行した場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法第1005条)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 208 検認の必要性
Q85
検認の手続きは非常に面倒なので自分ではできないのですが、これは必ずやらないといけないのですか?
A85
検認手続きを経ていない遺言書は、相続登記・預貯金の解約等の遺言執行の場面で使用できません。
そのため、面倒でも自筆証書遺言の検認手続きは必ず行う必要があります。
また、自筆証書遺言の検認手続きを経ていないことを不審に思う相続人が現れた場合、遺言執行手続きが順調に進まなくなる恐れもあります。
検認手続きでお困りの場合は、東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 206 検認と遺言内容の有効性
Q83
自筆証書遺言の検認をしたのですが、遺言書の内容に納得いきません。
遺言書の有効性について争うことはできないのですか?
A83
検認手続きは、遺言の有効性を確認・確定させる手続きではありません。
そのため、検認手続きの後、遺言の有効性や解釈について訴訟で争うことは、当然に可能です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 205 検認期日に立ち会わなかった相続人
Q82
自筆証書遺言の検認期日に相続人が立ち会わなかった場合、どうなりますか?
A82
申立人以外の相続人は、検認期日に立ち会わなくても構いません。
この場合、裁判所書記官は、立ち会わなかった相続人や受遺者などの利害関係人にその旨を通知します(家事事件手続規則115条2項)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 190 遺言の証人と遺言執行者
Q69
遺言執行者は遺言作成時の証人になることができますか?
A69
遺言執行者は遺言作成時の証人となることができます(大判大7・3・15)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 189 証人の欠格事由(遺言)
Q68
公正証書遺言を作成する場合には証人が必要と聞いたのですが、この証人になれない人というのは存在するのですか?
A68
以下の者は、証人や立会人になることができません(民法第974条,982条)。
(1)未成年者
(2)推定相続人及びその配偶者・直系血族
(3)受遺者及びその配偶者・直系血族
(4)公証人の配偶者
(5)4親等内の親族
(6)書記及び使用人

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 188 自筆証書遺言における自書
Q67
自筆証書遺言は自筆で書かなければならないと聞いたのですが、ワープロやタイプライターで書いてはいけないのですか?
A67
ワープロやタイプライターで書かれた場合、それは自筆証書遺言における「自書」にあたりません。あくまでも遺言者本人の筆跡が大事なので、ご自分で自筆証書遺言を作成される場合にはこの点十分にご注意ください。
また、余談ですが、カーボン紙を用いた複写の方法で記載された遺言は「自書」の要件を満たすものとされています(最判平5・10・19)
。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。